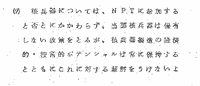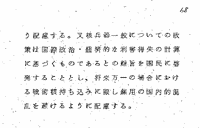- 米国の核実験、核の時代幕開け
- 5カ国目(中国)の核実験。中東情勢を背景にしたイスラエルの核開発
- 核不拡散条約(NPT)署名・発効:米露英仏中の5ヶ国を核兵器国と規定
- インドの核実験:核拡散防止体制の強化へ(核供給国グループ(NSG)誕生)
- イラン・イラク戦争:化学兵兵器禁止・ミサイル技術管理へ
- 湾岸戦争:大量兵器拡散防止体制強化へ
- 北朝鮮核疑惑:緊張から合意枠組みへ
- NPT無期限延長:包括的核実験禁止条約締結へ
- 印パ核実験。国連査察団イラクから追放で緊張
- 9.11同時多発テロとブッシュ米政権の強硬姿勢
- 2002年イラン核疑惑浮上。北朝鮮ウラン濃縮計画疑惑から合意枠組みの崩壊へ
- リビアの核兵器計画放棄宣言:カーン博士の闇市場問題浮上
- 参考リンク集
米国の核実験、核の時代幕開け
- 1945年
-
- 7月16日
- 米国、世界初の核実験(ニューメキシコ州アラマゴード)
- 8月6日
- 米国、広島に原爆投下
- 8月9日
- 米国、長崎に原爆投下
- 1949年
-
対共産圏諸国輸出規制に関する協議委員会、米国主導で開始
- 8月29日
- ソ連、初の核実験(カザフスタン共和国セミパラチンスク)
- 1950年
- 対共産圏輸出統制委員会(COCOM=ココム)設立
- 1952年
-
ココム内に中国を対象とするチンコム設立
- 10月3日
- 英国、初の核実験(オーストラリア西部モンテベロ島)
- 1953年
-
- 12月8日
- アイゼンハワー米大統領、国連総会で「平和のための原子力(Atoms for Peace)」演説(英文)
- 1957年
-
-
- 国際原子力機関(IAEA)設立
後に1970年発効の核不拡散条約(NPT)が、非核保有国は「IAEAの保障措置制度に従い、IAEAとの間で交渉しかつ締結する協定に定められる保障措置を受諾することを約束する」と規定。
- 1960年
-
- 2月13日
- フランス、初の核実験(アルジェリアのサハラ砂漠)
- 1962年
-
- 10月16日─28日
- キューバ危機
- 1963年
-
- 8月5日
- 部分的核実験禁止条約(大気圏内,宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約=PTBT)条文 (pdf)モスクワで作成
- 10月10日
- 部分的核実験禁止条約発効
5カ国目(中国)の核実験。中東情勢を背景にしたイスラエルの核開発
- 1964年
-
- 10月16日
- 中国、初の核実験(ウラン爆縮型:新疆ウイグル自治区ロプノール)
- 1967年
-
- 5月18日
- ウタント事務総長、シナイ半島からの「国連緊急軍(第1次UNEF)」撤退に同意
UNEFは、1956年のスエズ戦争(第2次中東戦争)以来駐留していたが、エジプトのナセル大統領が、14日と16日の二度に渡って撤退要求。
- 5月末
- イスラエル、最初の核兵器の組み立て?(NTI 英文)
(NTIの記事の典拠:Avner Cohen,Israel and the Bomb アマゾン)
(2006年に米国で機密解除された関連文書類:英文)
イスラエルは核保有を宣言していないが、100-200発保有と見られている
- 6月9日
- イスラエル、エジプトに攻撃開始(6日間戦争=第3次中東戦争)
核不拡散条約(NPT)署名・発効:米露英仏中の5ヶ国を核兵器国と規定
- 1968年
-
- 7月1日
- 核不拡散条約(NPT)署名開放 (寄託国:英ソ米)
条約で定める「核兵器国」とは、1967年1月1日以前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。
- 1969年
-
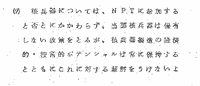
『わが国の外交政策大綱』p.67
- 9月25日
- 外務省「内部文書」『わが国の外交政策大綱』完成 外交政策企画委員会
(秘密指定解除された文書(pdf)、その1,その2,その3)
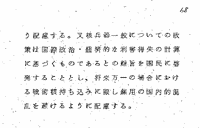
『わが国の外交政策大綱』p.68
- 琉球新報関連記事(抜粋入り:2010年2月21日)
- 一部を除いて開示すべきとの答申(2004年3月31日, pdf)
- 一部不開示は妥当との答申(2006年4月4日, pdf)
核兵器については、NPTに参加すると否とにかかわらず、当面核兵器は保有しない政策をとるが、核兵器の製造の経済的・技術的ポテンシャルは常に保持するとともにこれに対する掣肘をうけないよう配慮する。又核兵器一般についての政策は国際政治・経済的な利害得失の計算に基づくものであるとの趣旨を国民に啓発することとし、将来万一の場合における戦術核持ち込みに際し無用の国内的混乱を避けるように配慮する。
p.67 〜 p.68
- 1970年
-
- 3月5日
- 核不拡散条約(NPT) 発効
- 1972年
-
- 4月10日
- 生物兵器禁止条約(外務省訳, pdf)署名開放
正式名称は「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」。使用は1925年ジュネーブ議定書(「窒息性ガス、毒性ガスまたはこれらに類するガスおよび細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書」)で禁止されている。
- 5月8-9日
- パキスタンのカーン博士、初めて英独仏のウラン濃縮合弁会社ウレンコのアルメロ工場訪問。
(この年、ベルギーの大学で博士号を取得した博士は、ウレンコに主要機器を納入するアムステルダムのFDO社(特殊エンジニアリング)に就職)
インドの核実験:核拡散防止体制の強化へ(核供給国グループ(NSG)誕生)
- 1974年
-
- 5月18日
- インド核実験(米国提供の重水を利用したカナダ製サイラス炉で作ったプルトニウムを利用)
この実験後、核拡散を懸念した米国が原子力供給国グループ(NSG)設立を呼びかける
- 1975年
-
- 3月26日
- 生物兵器禁止条約(外務省訳, pdf)発効
- 9月3日
- ザンガー委員会の合意文書、IAEA文書(INFCIRC/209, pdf)として公表。
同委員会は、スイスのザンガー教授の提案で、NPT第3条2項の規制対象となる核物質、設備及び資材の解釈について協議するために設立され、1971年から74年にかけて協議し、合意文書を発表。合意文書は紳士協定的意味を持つ。現状を反映するため、その後も年2回の会合を開いて協議している。2008年末現在、37ヶ国が参加(リスト 英文)。最新合意文書 (pdf)は2008年2月4日に発表。
- 11月
- 原子力供給国グループ(NSG)、ロンドンで初会合(このため同グループはロンドン・グループとも呼ばれた)
- 1976年
-
- 5月24日
- 国会NPT承認
- 6月4日
- 日本、NPT批准書寄託
- 1978年
-
- 1月11日
- 原子力供給国グループ(NSG)、核関連輸出ガイドライン(パート1)(英文)を発表。(改訂版:英文, pdf)
(概要:外務省)
- 3月10日
- 米国核不拡散法(英文)制定
自国の原子力関連活動全体をIAEAの監視下に置く「包括的保障措置協定」をIAEAと結んでいない国への核関連輸出禁止。
イラン・イラク戦争:化学兵兵器禁止・ミサイル技術管理へ
- 1980年
-
- 9月22日
- イラン・イラク戦争(〜1988年)勃発
- 1984年
-
- 3月
- 国連の調査の結果、イラン・イラク戦争で化学兵器が使われたことが判明
- 1985年
-
- 3月
- イラン・イラク、双方の都市をミサイルで攻撃し合う
- 6月
- オーストラリア・グループ(英文)、(概説:外務省)設立総会
化学剤の輸出管理のためにオーストリアの提案で設立。後に生物兵器関連汎用品及び技術も規制の対象に。2008年末現在、40ヶ国プラス欧州委員会が参加(リスト 英文)。
- 12月12日
- 北朝鮮、NPTに加盟
- 1987年
-
- 2月8日
- 「核物質の防護に関する条約」(日本語)、(外務省対訳pdf)発効 (2005年改正案採択)
日本は、1988年10月に加入(11月に発効)
- 4月
- 「ミサイル技術管理レジーム(MTCR)」(英文)発足
(概説:外務省)
核兵器の運搬手段となるミサイル及関連汎用品・技術の輸出規制を目的に発足。1992年7月に生物・化学兵器を含む大量破壊兵器関連のミサイル及び関連汎用品・技術も規制対象に。2008年現在、34ヶ国が参加(リスト 英文)。搭載能力500キログラム以上かつ射程300キロメートル以上のロケット・システム及び部品・技術を特に規制。
湾岸戦争:大量兵器拡散防止体制強化へ
- 1990年
-
- 8月2日
- イラク、クウェートに侵攻。
- 1991年
-
- 1月17日
- 湾岸戦争始まる(多国籍軍、イラクを空爆)
- 3月3日
- イラク、暫定休戦協定受け入れ。
- 4月3日
- 国連安保理決議687(外務省仮訳, pdf)採択
イラクに対し大量破壊兵器の破棄を義務付け、国連大量破壊兵器廃棄特別委員会(UNSCOM)の設立を定める。
- 7月10日
- 南アフリカ、NPTに非核兵器国として加盟
- 12月25日
- ミハイル・ゴルバチョフ、ソ連大統領を辞任し、ソ連、崩壊。
ロシアがNPTの定める核兵器国に。他の旧ソ連構成国は次々に非核兵器国としてNPTに加盟。1994年12月5日のウクライナが最後。
- 1992年
-
- 3月9日
- 中国、NPTに加盟。
- 8月3日
- フランス、NPTに加盟 (NPTで定めた核兵器国5ヶ国中、最後に加盟)
北朝鮮核疑惑:緊張から合意枠組みへ
- 1993年
-
- 1月13日
- 化学兵器禁止条約(日本語訳:経産省サイト, pdf)
(概説:外務省)署名開放
化学兵器の開発、生産、保有などを包括的に禁止し、原則として10年以内に全廃を定める。使用は1925年ジュネーブ議定書が禁止。
- 3月12日
- 北朝鮮、NPT脱退声明(NPTは脱退声明の3ヵ月後に有効になると規定)
- 3月24日
- 南アフリカのデクラーク大統領、同国が核兵器を製造していたが、1991年7月10日までにすべて破壊と発表
ガンタイプの完成品6個と7個目の部品とを保有していた。
- 5月29日
- 北朝鮮、日本に向けてノドン実験
日本海に着水と報道。一発は太平洋に着水説有力。(この時点で、日本はほとんど射程に入る)
- 6月11日
- 米朝共同声明 (3月12日のNPT脱退表明が有効となる直前)
北朝鮮は、NPT脱退の「実現」を停止、宣言した7つの施設の査察に同意。米国は、核兵器を含む武力による威嚇・行使をしないと約束。
- 9月27日
- クリントン大統領、国連総会演説(英文)で大量破壊兵器の拡散が最も緊急の問題と主張
- 12月7日
- クリントン政権レス・アスピン国防長官、米国科学アカデミーでの演説(英文)で「拡散対抗構想」発表
旧ソ連の崩壊と技術の拡散という時代背景の重要性を指摘し、拡散防止の政策に加えて、拡散が起きてしまった場合に大量破壊兵器を持った相手と戦う「防護」政策が必要と強調。
- 1994年
-
- 10月21日
- 米朝、「合意枠組み」調印
- 12月5日
- ウクライナ、非核兵器国としてNPTに加盟。旧ソ連構成国の最後。
NPT無期限延長:包括的核実験禁止条約締結へ
- 1995年
-
- 4月17日−5月12日
- NPT再検討・延長会議で同条約無期限延長決定
- 1996年
-
- 7月
- ワッセナー・アレンジメント(英文)設立
(概説 外務省)
1994年3月に共産国を対象とした輸出規制体制ココムが解消されたのを受けて、通常兵器関連輸出管理のために設立。2008年現在40ヶ国が参加(リスト 英文)。名称は、1995年12月に協議が行われたオランダのワッセナー市にちなむ。
- 9月24日
- 包括的核実験禁止条約(CTBT)
(日本語訳 軍縮・不拡散促進センター, pdf)署名開放
(概要:外務省)
発効には高度な原子力技術を持つ44ヶ国の署名・批准が必要。2008年末現在この発効要件国のうち批准国は35ヶ国。残り9ヶ国のうち、未署名は、北朝鮮、インド、パキスタン。署名済みで未批准は、中国、エジプト、インドネシア、イラン、イスラエル、米国。(英仏ロは批准済み)。参考:CTBT概説・リンク等
- 1997年
-
- 4月29日
- 化学兵器禁止条約 (日本語訳:経産省サイト, pdf)発効
- 5月
- IAEA理事会、モデル追加議定書 (英文, pdf)採択
(99年発効日・IAEA追加議定書 日本語, pdf)
(概要:外務省)
IAEAとNPT加盟国の間で結ぶ保障措置協定の「追加議定書」は、IAEAの査察の権限を強化する協定。同モデル議定書の作成は、イラクによる秘密の核兵器計画や北朝鮮の核開発疑惑などがきっかけ。
印パ核実験。国連査察団イラクから追放で緊張
- 1998年
-
- 5月
- インド(11日と13日)・パキスタン(28日と30日:ウラン爆縮型)核実験
- 6月6日
- 国連安保理決議1172(外務省仮訳)
印パ両国に対し、核兵器を放棄し、非核兵器国としてNPTに加盟するよう求める。
- 10月
- イラク、国連大量破壊兵器廃棄特別委員会(UNSCOM)への協力の全面停止を決定(国連査察団、国外退去へ)
- 1999年
-
- 10月13日
- 米国上院、CTBTの批准案を否決
- 12月17日
- 国連安保理決議1284採択
イラクの大量破壊兵器廃棄に関し、UNSCOMに代わる国連監視検証査察委員会(UNMOVIC)(概要:外務省)設置を定めた。
- 2000年
-
- 3月1日
- ハンス・ブリックス前国際原子力機関(IAEA)事務局長がUNMOVIC委員長に就任
9.11同時多発テロとブッシュ米政権の強硬姿勢
- 2001年
-
- 7月
- 米国、生物兵器禁止条約の検証措置は有効でないとして検証議定書の交渉を拒絶
- 9月11日
- 米国同時多発テロ
- 10月7日
- 米英、アフガニスタン攻撃開始 (共同)
- 11月13日
- カブール陥落
- 12月5日
- アフガニスタン各派代表者、ボン合意
- 12月22日
- アフガニスタン暫定政権発足
- 2002年
-
- 7月16日
- ブッシュ大統領、国土安全保障戦略(英文, pdf)を発表(国務省発表声明の大使館訳)
「米国は、再びテロリストの奇襲を受けることのないよう、必要なあらゆる手段をとる。米国は、テロ活動を、テロ攻撃という形をとる前に察知できるような情報・諜報および警告システムを有することによって、適切な先制・予防・防衛行動をとることができるようにしなければならない。」
2002年イラン核疑惑浮上。北朝鮮ウラン濃縮計画疑惑から合意枠組みの崩壊へ
- 8月14日
- イランの反体制組織(イラン抵抗全国会議)、イランの核兵器開発計画指摘
- 9月17日
- 米国、国家安全保障戦略(大使館訳)発表。(英文, pdf)
「我が国の最大の危険は、過激主義と技術が交差するところにある。・・・常識として、また、自衛として、米国は、このような出現しつつある脅威に対して、それが完全に形成される前に行動する」
- 9月17日
- 日朝首脳会談 平壌宣言
- 10月16日
- 米国務省、北が「ウラン濃縮計画を有しているとの情報を得た」と発表
- 11月8日
- 国連安保理決議1441(英文と日本語訳 環境総合研究所)
イラクに対し、国連の大量破壊兵器査察団に即時、無条件かつ積極的な協力を行うよう要請
- 11月13日
- イラク、国連安保理決議1441受け入れ
- 11月27日
- 大量破壊兵器査察団(UNMOVIC及びIAEA)、イラクでの査察再開。
- 11月25日
- 「弾道ミサイルの拡散に立ち向かうための国際行動規範(ICOC)」(英文, pdf)正式採択(ハーグでの立ち上げ会合で)
- 12月9日
- 北朝鮮の「ソサン号」拿捕事件
スペインと米国の艦船がイエメン沖で国旗を掲げていない北朝鮮の「ソサン号」を拿捕・臨検し、スカッドミサイル15基ほかを発見。イエメンと北朝鮮が合法的輸入と主張し(朝鮮外務省代弁人:朝鮮新報)船は開放されイエメンに。
- 12月10日
- 米国、大量破壊兵器と戦う国家戦略(英文, pdf)、 (米国大使館訳)
「国家戦略の3つの柱」を 「WMDの使用と戦う拡散対抗」「WMDの拡散と戦う拡散防止の強化」「WMDの使用に対処する『結果管理』」と規定。(概説:核情報)
- 2003年
-
- 1月10日
- 北朝鮮、再度、NPT脱退宣言
NPTの規定だと脱退は3ヵ月後に有効になる。2005年のNPT再検討会議ではこれについて公式の決定を行っていない。2006年に北朝鮮は核実験。
- 2月14日
- 「テロと戦うための国家戦略」(英文, pdf)発表。(発表に当っての大統領声明 米国大使館訳)
「国際的なテロとの戦いは、困難で長期的なものとなる。今日、ほとんどすべての大陸に、そして米国を含めた数多くの国に、テロ細胞が存在する。この戦いにおける勝利は、米国民ならびに米国の協力者の勇気、力、そして不屈の精神にかかっている」(声明)
- 2月21−22日
- IAEA事務局長らがイラン訪問。イラン、IAEAに、2つのウラン濃縮プラントと兵器用プルトニウムの製造に適した原子炉に関連した計画の1部について初めて説明
- 3月18日
- 国連査察団、イラクから引き揚げ完了
- 3月19日
- 米英軍の空爆により、イラク戦争開始
- 4月23ー25日
- 米中朝、3ヶ国協議(於北京)==> 8月27ー29六ヶ国協議に
- 5月1日
- ブッシュ大統領大規模戦闘終結宣言
- 5月22日
- 国連安保理決議1483(財務省サイト掲載訳文, pdf)採択
米英によるイラクの統治権限の承認、経済制裁の解除。これを受けて、連合国暫定当局(CPA)が発足。
- 5月31日
- ブッシュ大統領、「拡散に対する安全保障構想(PSI)」(英文)を発表
(概要:外務省)
ポーランドのクラコフで、日、英、伊、蘭、豪、仏、独、スペイン、ポーランド、ポルトガルの10ヶ国に参加呼びかけ。各国が協力して情報交換・不審船の臨検体制の強化などを目指すが、現存の国際法の枠内での行動。2008年10月現在93ヶ国が参加(リスト英文)。
- 6月4日
- PSI構想の中心的人物のジョン・ボルトン国務次官(軍備管理・国際安全保障担当)、下院外交関係委員会での証言(英文, pdf)で構想を説明
- 7月13日
- イラク統治評議会が発足。(朝日新聞)
- 8月27ー29日
- 第一回六ヶ国協議
- 9月
- PSI阻止原則宣言 PSI第3回会合(於:パリ)(仮抄訳) 外務省
- 9月12日
- IAEA理事会決議「イラン・イスラム共和国におけるNPT保障措置協定の実施」
10月末までにIAEAが持つすべての疑問に答える措置をとることと、ウラン濃縮・プルトニウム抽出関連の活動をすべて中断することとを要求
- 12月18日
- イラン、IAEAとの間で追加議定書調印・暫定適用(未批准)
リビアの核兵器計画放棄宣言:カーン博士の闇市場問題浮上
- 2003年
-
- 12月19日
- リビア、化学・生物・核兵器計画を放棄すると発表。
- 12月27-29日
- IAEAの査察チーム、リビアに。
- 2004年
-
- 2月4日
- パキスタンのA・Q・カーン博士、リビアなどを巡る核の闇市場に関わっていたことを認める
- 2月11日
- ブッシュ大統領7つの核拡散防止措置提案 国防大学での演説 核情報訳
4月28日 国連安保理決議1540号(外務省仮訳) (pdf)採択(概要 外務省)
国連安保理決議1540データベース(英文) NTI
非国家主体による大量破壊兵器の取得を助けないようにすることを各国に義務付けたもの。国連憲章第7章(平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動)下の行動として。
- 5月22日
- 小泉首相再訪朝
- 5月31日〜6月1日
- PSIクラコフ一周年記念総会議長声明 外務省訳
- 6月28日
- イラクの連合国暫定当局(CPA)、イラク暫定政府に主権を移譲
- 10月6日
- 米調査団、イラクに大量破壊兵器なしとの最終報告(9月24日付 英文)を発表(朝日新聞)
- 11月14日
- イラン、英仏独と、濃縮関連活動・再処理活動を全面的に停止することに合意(パリ合意)
- 2005年
-
- 4月13日
- 「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」採択日本は、9月15日署名日本に関しては2007年9月2日発効(外務省告示及び条約文)
参考 概要:外務省pdf
米国NGO(NTI)による説明 英文pdf
- 7月8日
- 「核物質の防護に関する条約」の改正(外務省gif)採択(外務省報道官談話)、(外務省経緯・改正説明, pdf)
発効には3分の2の加入国の改正締結が必要なため未発効(締結国リスト英文pdf) (日本は未締結)
米国NGO(NTI)による説明(改正文を含む) 英文pdf
- 9月13〜19日
- 4回六カ国協議第2次会合
六ヶ国「共同声明」 (9月19日)
- 9月24日
- IAEA理事会、イランによる保障措置協定違反を認定し、再処理・濃縮活動の停止を求める決議(決議概説:外務省)採択
- 9月28日
- イラン議会、追加議定書の実施停止を政府に要求する決議採択
- 2006年
-
- 1月4日
- イラン、濃縮関連研究再開を宣言
- 2月4日
- IAEA、イランの核問題を安保理に報告することを決める決議
- 2月14日
- イラン、濃縮再開
- 5月20日
- イラク新政府発足
- 7月5日
- 北朝鮮、ミサイル連続発射実験
- 7月16日
- 国連安保理決議第1695号(北朝鮮ミサイル発射非難) 外務省訳
- 10月9日
- 北朝鮮核実験
- 10月15日
- 国連安保理決議第1718号(北朝鮮核実験非難) 外務省訳
- 7月31日
- 安保理決議第1696号(イラン核開発に関する初の決議)(訳文:「Soka国連支援ネットワーク(SUN)」)
(英文)
イランに対し、濃縮・再処理活動の停止を義務付け。国連加盟国に対し、イランのこれらの活動および弾道ミサイル開発に資する行動をとらないよう要請。国連憲章7章第41条(非軍事的措置)の下での制裁に言及。
- 12月23日
- 安保理決議第1737号(イラン核開発制裁)(訳文:「Soka国連支援ネットワーク(SUN)」)
(英文, pdf)
(概要:経産省, pdf)
イランに対し、濃縮・再処理・重水関連活動の停止を義務づけ。国連憲章第7 章第41条下の制裁措置を含む(関連団体の資産凍結など)
- 2007年
-
- 3月24日
- 安保理決議第1747号(イラン核開発制裁)「Soka国連支援ネットワーク(SUN)」
(英文, pdf)
資産凍結対象の追加や特定武器輸出規制など
- 6月29日
- UNMOVIC活動終了(AFP)
- 2008年
-
- 9月6日
- NSG、インドをそのガイドラインの例外措置とするステートメントを承認
- 10月11日
- 米国、北朝鮮に対するテロ支援国家の指定を解除すると発表
- 11月19日
- イランに関するIAEA事務局長報告書 (英文, pdf)
同報告書を解説した米国の「科学・国際安全保障研究所(ISIS)」が、12月2日、イランは2009年中に、核兵器1発分の高濃縮ウランを数ヶ月で製造する能力を達成と警告
- 2009年
-
- 5月25日
- 北朝鮮、2度目の核実験
- 6月12日
- 北朝鮮非難の国連安保理決議第1874号
- 9月24日
- 「核不拡散・核軍縮に関する安保理首脳会合」(オバマが議長)で決議第1887号(国連広報センター訳)
参考 鳩山新政権国連デビュー関連文書
- 2010年
-
- 4月12ー13日
- 核セキュリティー・サミット(外務省:概要・コミュニケ・日本ステートメント他)
「すべての脆弱な核物質の管理を4年以内に徹底する」というオバマ大統領の呼びかけを歓迎し、これに参加するとし、具体策を入れたコミュニケ採択。次回会合は2012年韓国。
●参考
総論
テロ
条約
国際的輸出規制体制
日本の輸出管理
拡散に対する安全保障構想(PSI)関連
ミサイル関係
イラン
イラク
南アフリカ
北朝鮮