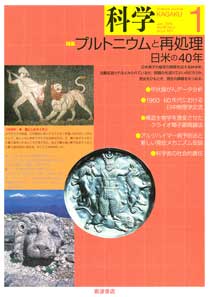
インドの1974年の最初の核実験を受けて米国は再処理推進策を変更しました。米国が協力した高速増殖炉計画で分離されたプルトニウムを使った実験だったからです。77年に登場したカーター政権は、東海再処理工場の運転を開始しようとしていた日本にも計画放棄を呼びかけます。2017年6月、当時の政権内部の議論内容を示す文書類が公開されました。これに関する米プリンストン大学のフランク・フォンヒッペルと核情報の共同論考(米核問題専門誌掲載)の日本語版を以下に再掲します。
参考:
- 六ヶ所再処理工場の製品で核兵器ができることを示す米国文書──1977年日米再処理交渉関係カーター図書館文書類 核情報 2011. 4. 4
- 日米原子力協定と反核運動 核情報 2018. 2.16
- 米専門家、プルトニウム増大をもたらす再処理政策中止をと訴え──使用済み燃料は再処理ではなく、敷地内乾式貯蔵を 核情報 2018. 4.27
行き詰まるプルトニウム問題:米国と日本の40年
田窪雅文・フランク・フォンヒッペル
初出:岩波書店『科学』(Jan.2018)(一部加筆・修正(小見出し追加他))
最近、カーター政権(1977~81年)内部で行れわた議論の内容を示す文書が公開された。プルトニウム分離プログラムを中止するように日本を説得することが可能か否かに関するものである。米国は国内で同様のプログラムを中止するという政策変更を実施しつつあった。しかし、日本はこのプログラムに深くコミットしていて、カーター大統領は両国の同盟関係が脅かされるようなレベルまで問題をエスカレートさせることを望まなかった。40年後の今日、日本のプログラムに対する経済環境核不拡散の面での反対論の説得力は強まっている一方、ウラン輸入への依存についての日本の懸念はひどく誇張されていたように見える。しかし、それにもかかわらず、プルトニウムの分離を続ける唯一の非核兵器国としての日本の先例は、他の国々における同様のプログラムの開始を正当化する役割を果たし続けている。これらの国々の中には核兵器オプションの獲得に関心をもつ国もあるかもしれない。
2017年6月、ワシントンD.C.の米国非営利団体「国家安全保障アーカイブ(NSA) 」が、40年前のカーター政権の内部文書類をそのサイトに載せた。(Japan Plutonium Overhang Origins and Dangers Debated by U.S. Officials, National Security Archive,Jun 8, 2017)日本にどのように働きかければ、原子力発電所から出てくる使用済み燃料の化学的再処理により分離済みプルトニウムを手に入れようという野心的プログラムを遅らせることができるかという論点を巡るものである。
インドの核実験の衝撃
外国の民生用プルトニウム・プログラムは、米国内の高次な政治的問題となっていた。インドが1974年に行なった最初の核実験において、増殖炉計画の初期装荷燃料のためという名目で分離されたプルトニウムを使った後、米国は、予測されるウラン不足の解消のために世界全体でプルトニウム増殖炉プログラムを推奨するという方針を転換した。増殖炉は、豊富な非核分裂性のウラン238を核分裂性のプルトニウムに変え、このプルトニウムを燃料として使おうというものである。通常の原子炉では、主として核分裂性のウラン235が燃料として使われる。ウラン235は天然ウランに0.7%しか含有されていない。
フォード政権(1974~77年)は、韓国とパキスタンに使用済み燃料の再処理工場を売ろうというフランスの計画を阻止したがほぼ完成していた東海パイロット再処理工場を放棄するよう日本を説得することには成功しなかった。そのため、1977年1月に登場したカーター政権は、日本との間のプルトニウムに関する難しい議論を受け継ぐことになった。
プルトニウムのMOX利用は非経済的──現在でも通用する国務省官僚の議論
今回新しく公開された文書類の中で一番古いのは、1977年1月24日付けの19ページのメモである。国務省の生え抜きの官僚ルイス・ノセンゾがカーター政権で新しく入ってくる政治任用官らに問題を簡潔に説明したものである。ノセンゾの議論は、40年ほど経った今、米国のNGOや「核分裂性物質に関する国際パネル(IPFM)」のような国際グループ、米国政府高官ら──最近ではオバマ政権の高官ら──が主張したものと驚くほど似ている。
これらの議論は、要約すると、プルトニウムを分離してこれを燃料として利用するという方法は,使用済み燃料を、その放射性発熱量が下がるのを待ちながら最終処分のための深地下処分場が建設されるまで、単に貯蔵しておくという方法に対して、経済的競争力をもちえないというものである。後者の「ワンス・スルー」燃料サイクルでは、プルトニウムは使用済み燃料の中で放射性の核分裂生成物と混ざったままに留まるから核兵器用に使うためのアクセスが比較的難しい。
ノセンゾは言う。プルトニウムを分離し、これをウランと混ぜて「混合酸化物(MOX)」燃料として軽水炉で再利用するのは同等量の低濃縮ウランを購人するのと比べ非経済的であり、この状況は少なくとも10年間は変わらない、と。実際は、その後の数十年間、ウランの長期的実質価格が下がり、再処理とMOX燃料製造に関連した職業安全性要件関係の費用が上がっていくなかで、コスト比較はMOXにとってますます不利になっていった。日本の原子力委員会の2011年の分析によると、日本の六ヶ所村の新しい再処理工場で分離されたプルトニウムで作るMOX燃料は、同等量の低濃縮ウラン燃料の12倍の費用がかかるという。
処分場のスペースが問題になるのはルクセンブルグぐらい
ノセンゾは次に、当時フランス、ドイツ、日本、スウェーデンが主張していた議論──現在もフランス、日本、そして、韓国の再処理推進派が主張している議論──に話を移す。再処理は、深地下処分を必要とする放射性廃棄物の量を95%減らすというものである。おそらくは皮肉を込めて、「スペースの制限が実際の問題となるのは、ルクセンブルクのような国だけだ」と彼は述べている(ルクセンブルクは米国のミズーリ州セントルイス市と同じぐらいの広さで、当時原子力計画をもっていなかった。現在もそうである)。
その後、高レベル廃棄物の地下処分場の容積を決めるのは廃棄物の容積ではなくその発熱量であることが指摘されている。廃棄物は、これを取り囲む緩衝材(粘土)や岩の温度の上昇を制限するために間を空けて設置する必要があるのである。再処理から出た廃棄物は、元の使用済み燃料に入っていた発熱性核分裂生成物のすべてを含んでいる。そして、1トンのMOX燃料を製造するのに、約7トンの使用済み低濃縮ウラン燃料を再処理して取り出したプルトニウムが使われるが、1トンの使用済みMOX燃料の発生熱量は、元の使用済み燃料に入っていたプルトニウムの発生熱量とほぽ等しい。一般に使用済みMOX燃料は再処理で出た高レベル廃棄物とおなじ地下処分場に入れられると予測されているが、その場合、容積の低減効果は得られないということである。
増殖炉の初期装荷燃料のためにプルトニウムを提供する必要性という問題に関しては、ノセンゾは、「増殖実験炉は現在、その初期装荷用にプルトニウムではなく、ウラン[連鎖反応を起こすウラン235を高度に濃縮したもの]を使っており、これはおそらく商業用増殖炉の運転開始に関しても続くだろう」と記している。(これは完全には正しくない。確かに米・ロ・中の実験・原型増殖炉は濃縮ウラン燃料で運転が開始されたし、また、すべての増殖炉で同じことをすることは可能ではあったが仏・日・英の原型炉の運転開始にはプルトニウムが使われた。)
米国の見解に同調する外国の官僚も使える「方針説明書」を
「米国の方針説明書を作成し、上記のような理論的説明をその根拠となる分析を添えて提示することがぜひとも必要だ」とノセンゾは述べている。「これは、例えば核供給国の文脈における他国政府との関係において、もっと一般的には……[米国の見解に]同調的な各国外務省が使うために有用だ──エネルギー、技術、経済関連の省庁に効果的に対処しようとする際に。」
最後のポイントは、日本本の通商産業省(現在の経済産業省)を含む世界各国の強大な力をもつ産業関連省の計画にとって増殖炉の推進が中核的なものとなっているという現実、そして、外務省は、極端だと思われる他の省庁の見解に対抗するために独立した立場からの分析を使う場合があるという現実を反映している。例えば、数年前、韓国の外務省の係官が、「韓国原子力研究所(KAERI)」──日本と同じ再処理の「権利」をという韓国の要求の原動力──を内密に「われわれのタリバン」と呼んだことがある。
東海再処理工場運転に固執する福田政権
日本は、この年の春に東海再処理工場の運転開始を計画していた。そして、ほぼ完成した工場の運転を阻止するのは不可能だろうというのはノセンゾには明らかと思われた。もう一つのメモは、福田首相が再処理を日本にとっての「死活」問題と公に呼んでいると述べている。日本政府は、1961年から71年まで米国原子力委員会委員長を務めたグレン・シーボーグが飽きることなく提唱した「プルトニウム経済」を達成することにコミットしていた。その「経済」においては、シーボーグ自身が共同発見した元素が世界の動力源となることになっていた。
福田政権はなぜプルトニウムの分離と使用をそれほど重要なものとみなしたのだろうか。首相は輸入ウランヘの依存は経済的脆弱性をもたらすとの説明を日本のプルトニウム推進派から受け、これを信じてしまっていたのだろうと私たちは推測する。1973年のアラブ諸国の石油禁輸措置の時に日本が経験したのと同様のものである。この経験は、当時まだ鮮明なつらい記憶だった。実際、日本によくある見方の一つでは、さらに遡った1941年に日本の真珠湾攻撃の引き金となったのは日本に対する米国の禁輸措置だったとされている。プルトニウム推進派は、資源に乏しい日本のウラン禁輸に対する脆弱性を増殖炉が解消すると主張した。増殖炉なら、すでに輸入されているウランをプルトニウム燃料のほぽ無尽蔵の供給源に変えてしまえるというわけである。
しかし、実際には過去40年間、ウランは豊富で安く、様々な国々から入手できる状態にあった。さらに、一部の外国人の専門家が指摘したように、日本が供給の途絶の可能性について本当に心配していたのなら、プルトニウム計画よりもずっと低いコストでウランの戦略備蓄50年分を得ることができたはずである。実際にも、世界的に見ると、電力会社はウランの低価格のおかげで約7年分の必要量を蓄積している。
1978年核不拡散法と日米原子力協力協定──日本が他国の計画の正当化に
米国の再処理・増殖炉開発プログラムを放棄するというカーター政権の提案を議会が受け入れるには数年かかったが議会は外国でのプルトニウム・プログラムを思いとどまらせようとする政権の取り組みは支持した。1978年核不拡散法は、他国との原子力協力協定の再交渉を行い、米国起源の使用済み燃料、あるいは米国の輸出規制の対象となっている部品または設計情報を有する原子炉で照射された使用済み燃料は、米国政府の事前同意なしには再処理できないようにしなければならないと定めた。しかし、カーター政権の内部では、原子力計画に関するこのような米国のコントロールを受け入れるよう同盟国に強いることができるかどうかについて意見が分かれていた。
「国家安全保障アーカイブ(NSA)」ファイルの最後のほうのメモの一つに、カーター政権の末期に「国家安全保障会議(NSC)」スタッフのジェリー・オプリンガーが書いたもの がある。オプリンガーは、カーター大統領の核不拡散担当特使ジェラルド・スミスの提案を批判している。スミスは西ヨーロッパと日本における使用済み燃料の再処理について包括的事前同意をカーター政権が与えることを提案していた。オプリンガーは、スミスの提案を「降伏」と見なした。ヨーロッパにおける、あるいは、日本によるさらなる核拡散の危険性は低いが、これらの国々の前例が他の国々によって自分たちのプルトニウム計画開始を正当化するために使われる可能性があるというのがオプリンガーの主張だった。
レーガン政権下での1988年日米原子力協力協定──2018年7月に満期に
カーター政権は日本や西ヨーロッパの再処理勢力に降伏しなかったが、1988年にレーガン政権が再交渉の結果署名した30年間の協定は、保障措置とプルトニウムの物理的防護に関する要件の追加と引き換えに、日本による再処理に完全な包括的事前同意を与えるものだった。68年の元の協定では、米国は、日本から英仏の再処理工場への使用済み燃料の輸送に関して、毎回ケース・バイ・ケースで検討する権利と、日本における再処理に関する共同決定をする権利とを認められていた。この権利によって、米国は、日本が分離済みプルトニウムをさらに必要とするかどうかについて問うことができる状態にあった。だが、88年の協定の結果、2011年の福島原発事故の頃には、日本は約44トンの分離済みプルトニウムを蓄積していた。長崎型原爆5000発分以上に相当する量である。そして、1年間で原子炉に装荷することのできた最大量(2010年)のMOX燃料に含まれていたプルトニウムは約1トンに過ぎなかった。(協定関連資料)
1988年協定の最初の有効期間は2018年7月に満期を迎える。その後は、どちらかの国が6カ月前に文書で通告すれば協定を終了させることができる。これは、米国政府にとって日本との間で再処理問題を再度持ち出す機会が存在するということを意味する。
1968年の日本との協定と異なり、58年米・ユーラトム(EURATOM=欧州原子力共同体)協定には、西ヨーロッパにおけるヨーロッパ側の使用済み燃料の再処理に関して米国側の事前同意が必要との規定はなかった。ヨーロッパ諸国が協定の再交渉を拒否したため、カーター大統領を皮切りに歴代の米国大統領は米・ユーラトム協定を大統領令で延長するという形で対処した。最終的には、95年にクリントン政権が新しい協定の文言について交渉した。ヨーロッパの再処理国がこれを不干渉の約束とみなして受け入れた。このころまでには、ヨーロッパの非核兵器国──とりわけドイツおよびイタリア──は増硝炉に対する関心を失っており、協定のリストに載せられた再処理工場は英仏のものだけだった。日本の再処理推進派はしばしば、日本は国際社会に信頼されて再処理を許されている唯一の非核兵器国だと主張する。だが、実際は、経済性の悪さにもかかわらず再処理を放棄するに至っていない唯一の非核兵器国なのである。
予測された大量の民生用分離済みプルトニウムの蓄積
オプリンガーが指摘した通り、日本は国内の再処理だけでなく、ヨーロッパにおける大規模な再処理の維持に中核的な役割を果たした。日本の電力会社は、再処理契約の前払いという形で仏英の新しい大型商業用再処理工場の建設の資金を提供した。また、フランスは再処理の推進と日本の再処理工場の設計に関し中心的な役割を果たした。オプリンガーは、ヨーロッパと日本における再処理計画は、増殖炉計画の必要量を超えた大量の余剰分離済みプルトニウムを生み出すことになると主張した。「計画されているこれらの三つの再処理工場のどの一つをとっても、世界のすべての高速増殖炉計画のプルトニウム必要量を圧倒する。三つ合わせれば膨大な余剰を生み出し……2000年までに数百トンに達する。」
彼は、2000年までの状況についてのグラフを添付している。三つの工場が、増殖炉の研究開発の必要量を超えた370トンの余剰分離済みプルトニウムを生み出すことを示すものである。2000年のヨーロッパと日本における民生用分離済みプルトニウムの実際の量は非常に大きいものになった。核兵器1発あたり8kgというIAEAの計算方式を使えば、長崎型原爆2万発分に相当する。しかし、それは、オプリンガーのメモで予測された量の約半分だった。これは、一つには、英国の再処理工場の稼働率の問題、それに、日本の大型再処理工場[六ヶ所再処理工場]の運転の遅れのためである。需要の側はというと、増殖炉による利用は想定されたよりもずっと少なかったが、余剰に対処しようということで、相当鼠のプルトニウムがMOX燃料にされヨーロッパの通常の原子炉で照射された。
もんじゅがダメならアストリッドがあるさ?
40年を経た今、日本の増殖炉計画──元々の再処理計画の正当化に使われたもの──は実質的に息絶えている。日本は2016年に高速増殖原型炉もんじゅを公式に放棄した。1995年の二次冷却系ナトリウム漏れとそれにともなう火災の後、約20年間にわたって再稼働させようと試みた末のことである。日本政府は、今度は、フランスにおけるアストリッド(ASTRID=工業的実証用改良型ナトリウム技術炉)の建設計画に参加するという話をしている。フランスの原子力関係者は費用の一部を日本が負担するというアイデアを歓迎している。だがアストリッド型の高速中性子炉の役割は、使用済みの低濃縮ウラン燃料やMOX燃料に含まれるプルトニウムなどの長寿命の超ウラン元素を核分裂させることにある。このためには日本は新しい再処理工場を建てなければならない。また、フランスの2006年の放射性廃棄物法によると、アストリッドは、2020年までに運転開始となるはずだったが、その予算は2019年までしか確保されていない。さらに、アストリッド計画の責任者は2016年10月に東京で行った説明において「調整期間」が2020年に始まるというスケジュールを示した。その翌日、東京のフランス大使館の原子力問題責任者は、アストリッドの運転開始は2033年以降と語っている(毎日新聞2016年10月27日 )。つまり、予定が10年間で13年延びたのである。(スケジュールの変遷)
増殖炉も軽水炉でのプルトニウム利用も経済性がないということはこの40年間で明らかになっている。六ヶ所再処理工場の総費用の最新の見積り額は、建設費、40年間の運転、廃止措置を合わせて、13.9兆円(1250億ドル)となっている。建設費だけで2.95兆円(270億ドル)に達している。これには,福島原発事故後の新しい安全性規制による改修費0.75兆円が含まれる。MOX燃料製造施設の総コストは約42年の運転と廃止措置の費用を含めて、2.3兆円(210億ドル)と見積もられている。
米国では、1977年に再処理と増殖炉が経済的に意味をなさず、核拡散の悪夢をもたらすということが明らかになってからわずか5年ほどで、政府と電力会社が両方の計画を放棄することに合意した。産業側がすでに、2017年のドルにして、約13億ドルをサウス・カロライナ州の再処理工場の建設に、政府が42億ドルをクリンチリバー増殖実証炉計画につぎ込んでいたにもかかわらずである。
日米の関心の方向のずれ──核不拡散に無頓着な被爆国日本
日本政府は、どうして、非常に高くつくプルトニウム計画を電力会社が40年以上追求し続けるという状態を再処理推進派がもたらすのを許してしまったのか。まず、全体像を把握するには、米国は、核超大国として、核拡散・核テロについて日本よりもずっと心配してきたということを想起しなければならない。1988年協定の交渉に関わった遠藤哲也元大使は、両国政府の態度の違いを次のように述べている。
「この協定の是非に対する米側、特に米政府の判断基準が安全保障(核不拡散はその一面である)であったのに対し、日本側のそれは原子カエネルギー問題であった……。図式的に言えば、安全保障対エネルギー確保とでも言うか、関心の方向がずれているように感じられた。」(日米原子力協定(1988年)の成立経緯と今後の問題点(改訂版:2014年1月)(pdf)
すでに見たように、米国では、インドの1974年の核実験の後、フォード政権もカーター政権も、再処理の普及を非常に深刻な安全保障問題と捉えた。実際、英国に使用済み燃料を運ぶために1976年10月16日に敦賀原子力発電所の岸壁に接岸した船が、フォード政権の反対により9日間出港できないという事態が生じている。日本では、核拡散・核テロに関する米国の懸念は、全体として、世界最大級の核兵器をもつ国による日本のエネルギー政策に対する介入とみなされた。再処理に反対している国会議員や、反核運動活動家、マスコミの目さえも、この愛国主義的な感情により曇ることがあった。
使用済み燃料貯蔵スペースと再処理──福島事故が示した乾式貯蔵の必要性
しかし、それでも、再処理は膨大な費用をともなうものであり、日本政府が電力会社にこのコストを受け入れさせることをいとわない理由は何かという検討は必要である。
日本の原子力委員会が提示した一つの説明は、原子炉の敷地内における使用済み燃料の無期限の保管について地元自治体と交渉することの政治的難しさを巡るものである。政府と電力会社は、原発の受け入れ市町村および県に対して、使用済み燃料は敷地から持ち出すと約束してきた。再処理政策は、行き先を提供する。最初はヨーロッパ、東海再処理パイロット・プラント、そして、六ヶ所再処理工場である。日本の原子力委員会は、使用済み燃料の敷地内無期限貯蔵の交渉には何年もかかるだろうから、その間に、使用済み燃料の行き場のなくなった原発が次々と閉鎖されることになり、それは、再処理コストをさらに上回る経済的損失をもたらすと主張した。
原発をもつ日本の電力会社はいずれにしても使用済み燃料の敷地内貯蔵能力を拡大しなければならなかった。六ヶ所再処理工場の運転開始の遅れのためである。同工場は、当初計画では1997年に商業運転を開始することになっていたのである。実際、電力会社は、使用済み燃料冷却プールに使用済み燃料集合体を詰め込む「デンス・パッキング(稠密貯蔵)」という米国の危険なやり方を採用してきた。使用済み燃料を自然の対流により冷却する乾式キャスク貯蔵のほうが、敷地内であれ敷地外であれ、ずっと安全である。米国では、使用済み燃料は、稠密貯蔵のプールが完全に満杯になった時点で敷地内乾式貯蔵に移される。この移動を使用済み燃料が乾式貯蔵できる温度に下がり次第行うほうがいい。このような乾式キャスク貯蔵加速化という政策への移行を可能にするためには、両国における原子力安全規制の強化が必要である。
日米官僚機構の違いと地域独占
第二に、官僚体制面での説明がある。日本では、米国よりも官僚機構が政策について大きな力をもっている。日本では国会で新しい総理大臣が選出されると、大臣だけが変わるが、2大政党制をとる米国では、政策決定は、議会と行政府が分け合う度合いが大きい。そして、新しい大統領は、官僚機構の上部で4000人以上の係官を入れ替えることが普通である(これは、現在の米国政府に見られるように、いいほうに機能する場合とそうでない場合がある)。日本ではまた,米国と異なり、官僚機構は閉じられている。官僚機構の中に入ったり出たりという経歴の交差はほとんどない。
第三に、日本では電力供給は規制の強い地域独占の形をとってきた。したがって、電力会社は、再処理の余分な費用を消費者に回し、自らの利潤の浸食を避けることができた。この独占構造は、電力会社に地方と全国の両面で膨大な政治的力を与え、選挙結果と政策決定過程の両方で影響力をもつことを可能にしてきた。その結果、元々の再処理政策は官僚機構が作ったものであったとしても、この複雑に絡み合った影響力の相互作用の網のために、今やこれを変えることが非常に難しくなっている。
日本は、徐々に自由化に向けて動いている。とりわけ、福島原発事故以降はそうである。しかし、最近、この流れに逆行する形で再処理を確実にするための法律が制定されている。使用済み燃料の再処理と、それによって回収されたプルトニウムを使ったMOX燃料製造の費用を、元の燃料の照射の時点で払うことを電力会社に義務付けるものである。自由化された市場において余分な費用を払うことを強いるこの法律に、原発をもつ電力会社が公に反対しなかったということは、原発をもたない発電事業者の電力を買う消費者にも広くコスト負担させるシステムを政府が構築することを期待しているのだろうと思わせる。例えば、規制の対象となり続ける送電・配電に上乗せするというような方法である。
フランス、インド、ロシアでもプルトニウム分離計画が存続している。中国も、何十年間も再処理政策を維持している。ただし、小さな産業用再処理工場の計画が敷地準備段階に達しただけで、フランスから購入するという大型の再処理工場の計画のほうはまだ敷地が見つかっていない。これらの国々では、日本と同じく、中央官僚機構が大きな力をもっている。フランスの政府所有の電力会社は、選択の権利のあるところでは再処理から抜け出すことを明確にしている。英国における状況がそれ──同社は英国の原発も運転しているの──である。英国ではあと数年で既存の契約が完了すれば再処理に終止符が打たれることになる理由の一つがここにある。
核兵器オプション?──逆効果
なぜ日本においてプルトニウムがしぶとく生き残っているかについて時折出される最後の説明は、日本の安全保障エスタブリッシュメントが核兵器のオプションを維持したがっているためだというものである。しかし、日本にはすでに分離済みプルトニウムが約10トンある。それに加えて仏英両国には日本のプルトニウムが37トンある。年間8トンのプルトニウム──毎年核弾頭1000発分──を分離するという六ヶ所再処理工場の設計能力は、核兵器オプションのために必要なレベルをはるかに上回っている。そのうえ、日本はすでに、イランが計画していたものよりずっと大きな規模の遠心分離濃縮プラントをもっている。イランの計画はその核拡散の懸念のため国際的危機をもたらした。日本のプラントはイランのものと同じく、原発用の低濃縮ウランを製造する設計となっている。しかし、カスケードの並び替えによって毎年10発分の兵器級高濃縮ウランを天然ウランから製造することができる。日本はこの濃縮能力を10倍以上にする計画である。だから、日本の安全保障担当者らが膨大なコストを伴う六ヶ所再処理計画を秘密裏に推進しているからこの計画が続いているというのは信じがたい。
しかしながら、日本が核兵器オプションを維持しているという話自体が、日本の安全保障にとって悪影響をもたらす。周辺国に疑念を抱かせ、韓国においても核兵器オプションを取得すべきだという同国内の議論を正当化する。また、核軍縮にとって障害となる。ニューヨーク・タイムズによると、オバマ大統領が退任前に先制不使用政策の採用を検討した際、ジョン・ケリー国務長官が「米国の核の傘のいかなる縮小も日本を不安にさせ,独自の核武装に向かわせるかもしれないと主張した」という。そろそろ日本の安全保障担当者も核兵器反対運動も、このような懸念を真剣に検討すべきだろう。
終わりに
再処理の経済性のひどさからすると、日仏両国におけるその終焉は時間の問題だろう。しかし、日本の計画を巡る40年にわたる対峙・膠着状態が示しているように、必然的なものが現実となるのに非常に長い時間がかかることもある。その間に費用と危険性が高まり続ける。日仏がその破綻状態の再処理プログラムの放棄を頑なに拒否しているにもかかわらず、プルトニウム・プログラムの拡散やテロリストによる両国のプルトニウムの盗取や使用が起きていないのは、世界にとって幸運だった。再処理の「権利」を求めるソウルからの圧力は、反原発の考えをもつ文在寅大統領が選出されたことで弱まるかもしれない。経済性の「見えざる手」と米国の政策の両者の組み合わせは、日本以外の国への再処理の普及を防ぐうえで極めて効果的だったと言える。しかし国際的な原子力産業における中国の影響力の増大とその再処理プログラム──フランスの設計の大規模再処理工場の建設を含む──は,この核不拡散の成功物語にとって新たなチャレンジを突きつける。完全に破綻した再処理プログラムを政府の提供する高額の救命措置から外すという決定をフランスと日本が行えば中国にその政策を再考するよう説得できることになるかもしれない。
田窪雅文 「核情報」主宰。「核分裂性物質に関する国際パネル(IPFM)」メンバー。プリンストン大学「科学・世界安全保障プログラム」コンサルタント
フランク・フォンヒッペル Frank von Hippel 核物理学者。プリンストン大学上級研究物理学者、公共・国際問題名営教授。1975年に同大学で現在の「科学・世界安全保障プログラム」の前身を共同設立し、30年間にわたって共同議長を務めた。2006年に「核分裂性物質に関する国際パネル(IPFM)」を共同設立し、8年間共同議長を務めた
*本稿の注・文献を含む英文原稿(核情報) 英語版の初出は Bulletin of the Atomic Scientists (3 SEPTEMBER 2017)