一年前の7月16日、米国起源の使用済み燃料を日本が再処理してプルトニウムを取り出すことを一括して認める日米原子力協力協定が30年の効力期限を迎えて、期限を定めない形で自動延長されました。これと前後して、7月3日に閣議決定されたエネルギー基本計画に「プルトニウム保有量の削減に取り組む」という文言が入り、7月31日に原子力委員会が発表した方針が、我が国は「プルトニウム保有量を減少させる。プルトニウム保有量は…現在の水準を超えることはない」と宣言しました。この「新方針」は、国際原子力機関(IAEA)の計算方法で核兵器約6000発分という日本のプルトニウム保有に懸念を抱く米国の圧力によってもたらされたと見られていますが、本当に六ヶ所再処理工場を運転しながら削減が可能なのか。「新方針」が、再処理政策正当化のためのこれまで通りの単なる宣言に終わってしまわない保証は? 以下、「新方針」が出てきた背景を概観し、問題点を確認した後、1990年代からの流れを略年表形式で整理します。そして、最後に関連資料を載せておきます。
平和利用について聞かれて面食らう日本原燃と混乱の背景
電力会社が主要株主となっている日本原燃は、六ヶ所再処理工場を2021年秋(21年度上期)までに完成させ、翌22年初めから運転開始しようとしています。数年でフル操業を達成し、年間約7トンのプルトニウムを分離する計画です(設計分離能力は約8トン:実際の分離量は、原子炉で燃料を燃やした期間、取り出し後の冷却期間などによる。詳細は以下「六ヶ所再処理工場における年間プルトニウム分離量」を参照)。
その日本原燃に原子力規制委員会が2016年12月14日の臨時会議で尋ねています。
田中知委員「再処理の事業者として、自らが分離するプルトニウムが平和利用目的のないプルトニウムかどうかを今後どう判断していくのか…判断基準?」
更田豊志委員長代理「要するに、どういう状態のプルトニウムがどれだけたまると過剰ということになるのかと。それは自社で判断をされるのか、あるいはどこかの判断を仰ぐことになるのか」
(本来なら、政府関係機関が判断基準について定め、指示が出されるはずの「利用目的のないプルトニウム」について、規制委から「おたくはどう判断するのですか」と聞かれ、面食らったようです。(延々と続くやり取りについては、この記事の一番下に掲載の原子力規制委員会第49回臨時会議議事録 関連部分抜粋を参照)
珍問答の末、やっと質問の意味を理解した日本原燃側は質問で返します。
工藤健二社長「それは私どもだけではなくて、国際の話につながるわけで…御当局というのは、どこが?」
田中俊一委員長「利用目的のないプルトニウム…どこが一体それを決めるのか」
更田委員長代理「原子力委員会は平和利用目的の事業であるという観点から判断をされるのだろう…が…これは日本原燃がやる事業であるからといった理由で平和利用目的だという判断はなかなか下しづらい…」
福島事故を受けて2012年9月に発足した原子力規制委員会は「国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること」をその任務の一つとしています。近藤駿介原子力委員会委員長(当時)も、翌13年に原子力委のあり方について議論された際、規制委設置法から言って原子力の「平和の目的への限定」は規制委の「所掌となったと解するべき…ただし、このことについて規制委員会の意思を確認するまでの間は、原子力委員会が管理する」と述べています。
ところが「あり方検討」の結果、原子力委の所轄を原子力の平和利用(軍事利用しないこと)の確保と放射性廃棄物の処理処分などに限るようにとの提案が同年12月に有識者会議から出されます。翌14年12月16日、改正原子力委員会設置法に基づく新体制の原子力委が活動を始めるに当たって、岡芳明委員長は「原子力の平和利用、放射性廃棄物の処理・処分等の原子力利用に関する政策の重要事項に焦点を当てて、国民の目線で取り組んでまいります」と意思表明をします。ここに混乱の種の一つがあります。
この後、2016年5月、経産省管轄の再処理専門認可法人を作り、使用済み燃料発生時にその再処理費用を払い込ませるという「再処理等拠出金法」が成立し、同10月に再処理機構が設立されます。前年10月14日、規制委の会議で認可法人の利点について説明を求められた経産省は、認可法人になれば、再処理計画に経産省が介入してプルトニウム・バランスを管理できると説明しています。そして、同法が採択された際の衆参両院の附帯決議には、「認可法人が策定する再処理等事業の実施中期計画を経済産業大臣が認可する際には、原子力の平和利用やプルトニウムの需給バランス確保の観点から、原子力委員会の意見を聴くものとし、その意見を十分に斟酌して認可の適否を判断するものとすること」とあります。
日本政府関係者が米国の政府関係者や再処理批判派に対し、この認可法人の仕組みによってプルトニウムの需給バランスを調整できるから六ヶ所再処理工場の運転を開始してもプルトニウムの量が増えることはないと説明しているという話が核情報にも届いていました。しかし、そもそも、日本政府は、1991年に「必要な量以上のプルトニウムを持たないようにすることを原則とする」との方針を示し、1997年には「我が国において計画遂行に必要な量以上のプルトニウム、すなわち、余剰プルトニウムを持たないとの原則」を国際原子力(IAEA)に送った文書で国際的に宣言していました。ところが、国際的宣言から20年近くたっても、核セキュリティーや「平和利用の確保」に責任を持つはずの規制委が、「余剰プルトニウム」とは何かを誰がいかなる基準で判断するのかも、分からないと言っている状況だったのです。(2006年の経産省の考え方については次を参照。 余剰プルトニウムの定義に関する2006年3月13日経産省回答 「余剰プルトニウムというのは量的概念ではない」)
そこで、問題の臨時会議開催から4か月後の2017年4月、規制委が原子力委に、判断するのはおたくですかと尋ねることになります。後者が「はい」と答え、上記の附帯決議に触れ、プルトニウムの需給バランス確保について確認し「必要に応じて経済産業大臣、電気事業者、再処理関連事業者等に対して意見を示す」と応じました。(原子力委は、実はプルトニウムの需給バランス確保についての確認は2003年からやっていたはずだが、その方式が効力を持たないものであったことについては、 古い虚構から新たな虚構へ? 検証の試みを参照。)
六ヶ所再処理工場の適切な在庫は60トン?
これで役割分担が明確化されたかに見えますが、在庫がどのくらい膨らめば利用目的のないプルトニウムとなるのかについての「判断基準」はどうするのかという規制委の問いに対する答えはでていません。この問いについて、2016年の臨時会議で村上秀明副社長は「MOX工場[用]の在庫としてはどのぐらいが適切かという議論があり…在庫としては60トンHM[形状は金属酸化物の粉末となっている]」と述べています。日経産業新聞の記事(2019年3月19日)によると、規制委も政府関係者もこれをプルトニウム60トンと捉えた可能性がありますが、だとすると、それは誤解でしょう。
再処理工場では、プルトニウムとウランを1:1で混ぜた混合酸化物(MOX)製品(粉末)が製造されます。これを隣接して建設中のMOX燃料製造工場でウランと混ぜてMOX燃料を作ります。副社長の発言は意味が把握しづらいのですが、言及しているのは六ヶ所再処理工場のMOX製品の在庫貯蔵容量のことで、プルトニウムとウランの合計量60トンのことと思われます(HMはheavy metal=重金属を意味し、混合酸化物の酸素を除いた重量ということ)。プルトニウムだけだと30トンになります。再処理工場に30トンのプルトニウムを在庫として持つことが認められているので、これを基準に考えるべきだとの説明と見られます。これにMOX燃料製造工場の在庫を合わせた量が六ヶ所施設に存在しても、許容されるべきというのが日本原燃の主張のようです。仮に、これを合わせて約40トンとして考えてみましょう。
現在の水準を超えないとする原子力委の宣言と日本原燃の主張は両立できるのか。2017年末現在、日本のプルトニウム保有量は、再処理委託した英仏(37.3トン:英国で追加割り当て予定の0.6トンを含む)と日本国内(10.5トン)合わせて約48トン。日本の各原発にある未照射のMOX燃料2.3トンと英仏保管分37.3トンを合わると約40トンになります。この全量を急いで日本の原発で燃やしてゼロにし、同時に、それと同量の40トンが六ヶ所の在庫としてたまったとしましょう。そうすると、「現在の水準を超えること」なく、48トンの大半が核兵器国の英仏に保管という現在の状態から、48トンすべてが日本国内保管という状態に移行します。これで非核兵器国の日本が核兵器6000発分のプルトニウムを抱える状況についての国際的な懸念の払しょくになると考えるのでしょうか。そうでないなら、どのような過程を原子力委は想定しているのでしょうか。どのようにして、プルトニウムの削減が実現できると判断しているのでしょうか。その想定を規制委は妥当と判断しているのでしょうか。経産省は? 日本政府は?
また、約22トンを保管する英国にはMOX燃料製造工場がありません。この22トンをどうするのか。フランスに送ってMOX燃料にして日本に輸送? 英国にお金を払ってゴミとして処分を委託? その一方で日本でさらにプルトニウムを分離? そして、規制委は原子力委からの「担当はうち」との返答で核セキュリティー・平和利用について持つ責任から逃れられたと考えているのか。両委員会や日本政府には、これらについて明確に説明する責任があります。国会やマスコミは、このような問題点を念頭に、削減宣言の実態を明らかにしていかなければなりません。
余剰プルトニウム問題略年表式整理
- 1991年
- 原子力委員会核燃料専門部会報告書『我が国における核燃料リサイクルについて』発表
*「必要な量以上のプルトニウムを持たないようにすることを原則とする」と宣言 - 1993年4月28日
- 六ヶ所再処理工場着工
- 1995年12月8日
- 高速増殖炉もんじゅナトリウム漏れ事故
- 1997年
- (元の六ヶ所再処理工場完成予定の年)
- 2月4日
- プルトニウムを普通の原子炉で燃やす「プルサーマル」推進を閣議了承
- 2月21日
- 電事連、『今後の原子燃料サイクルの推進について』発表
*2010年までに16~18基でプルサーマル導入(年間7~11トン消費)という計画。年間8トンのプルトニウム分離能力を持つ六ヶ所再処理工場の運転を正当化しようとするもの。 - 12月
- 日本政府、「余剰プルトニウムを持たないとの原則」を国際原子力(IAEA)に送った文書で国際的に宣言
- 2003年8月5日
- 原子力委、「わが国のプルトニウム利用の基本的考え方」(pdf)決定
*「利用目的のないプルトニウム、すなわち余剰プルトニウムを持たないとの原則」を再確認するとともに、間近に控えた六ヶ所再処理工場の試運転開始を念頭に、電気事業者は、プルトニウムの詳細な利用計画(利用開始時期・期間を含む)を毎年度プルトニウムの分離前に公表すると定める。 - 2011年12月1日
- 英国、日本がお金を払えば、英国保管の日本のプルトニウムの「所有」を英国に移して、処分を引き受けてもいいとオファー
*同政策について駐日英国大使館が翌2012年12月21日の原子力委臨時定例会議において説明: 『英国のプルトニウム管理について』(pdf) 議事録(pdf) - 2012年6月20日
- 原子力規制委員会設置法、参議院本会議において可決・成立
第四条
原子力規制委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
…四 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
- 9月19日
- 原子力規制委員会発足
- 2013年8月8日
- 近藤原子力委員会委員長、平和利用は規制委の所掌との見解表明
*原子力委員会の在り方見直しのための有識者会議(第2回)提出資料(P11~12)(5)原子炉等規制法の改正により、平和の目的への限定を確かなものにするこれらの取組の企画・推進は原子力規制委員会の所掌となったと解するべきであり、こうした慫慂(誘導)の取組も、今後は規制委員会において主体的に行われるものと理解している。ただし、このことについて規制委員会の意思を確認するまでの間は、原子力委員会が管理する。
- 12月10日
- 「原子力委員会の在り方見直しについて」有識者会議報告発表
*委員の数を5人から3人に縮小すると同時に、その役割を原子力の平和利用(軍事利用しないこと)の確保と放射性廃棄物の処理処分などに限るという提案③平和利用に関する政策について
我が国が原子力利用を平和目的に限って行うに当たり、プルトニウム利用・管理の透明性の向上のための取組は今後とも重要な事務の一つであり、これを実施する意義がある。平和利用、核不拡散等に係る政策の観点から、ウラン濃縮を含む核燃料サイクル政策等についても独自の立場から意見を言うことが考えられる。
なお、海外プルトニウムの保管量の確認は、保障措置における国内プルトニウムの保管量の把握と併せ、原子炉の平和目的利用の審査を行っている原子力規制委員会が、原子炉等規制法に基づく報告を徴収することなどにより、法的根拠を有したものとすることが望ましい。
また、現在、原子力委員会が行っているプルトニウム利用目的の妥当性の確認(将来のプルトニウム利用計画の確認)は、電気事業者等の公表資料をもとに行うのではなく、原子力委員会設置法に基づき、経済産業省、文部科学省を通じて電気事業者等から必要な資料の提出を求めるなど、根拠を明らかにした形での確認とすることが望ましい。
- 2014年3月
- 安倍首相、オバマ大統領とともに、「高濃縮ウランとプルトニウムの最小化のために何ができるかを各国に検討するよう奨励」
*オランダ・ハーグ開催の核セキュリティー・サミットの日米首脳共同声明 - 12月16日
- 岡原子力委委員長、平和利用確保に取り組むと発言
*改正原子力委員会設置法施行に当たって原子力の平和利用、放射性廃棄物の処理・処分等の原子力利用に関する政策の重要事項に焦点を当てて、国民の目線で取り組んでまいります。
- 2015年10月14日
- 経産省、再処理等拠出金法を制定し再処理主体を認可法人にすることにより、再処理計画に政府が介入してプルトニウム・バランスを管理できると説明。
*規制委会議で、経産省の資料に以下のようにあることの意味を問われて。 「核不拡散上も重要な再処理等が適切な体制の下で確実に実施される仕組みとすべき。 ○ このため、実施主体については、民間主導で設立される一方で、国が必要な関与を行うことができる「認可法人」とすることを念頭に検討を進めるべきではないか。」分かりやすく申し上げれば、再処理事業から発生するプルトニウムを適切に管理していかなければいけない。我が国全体として、余剰プルトニウムは持たないという大原則の下で、この再処理事業を行っていくことにしているわけでありますが、プルトニウムが発生する量、それからプルトニウムを燃やす量と言いますか、MOX燃料としてそれを発電に使うという使用の量との関係が、バランスが損なわれることがないようにしっかりとしていかなければいけない、そうしたところに大きな問題意識を持ちながら、核不拡散上重要な再処理事業について、しっかりと適切な管理をしていく
- 2016年4月20日
- 衆院、5月10日参院、再処理等拠出金法附帯決議
四 認可法人が策定する再処理等事業の実施中期計画を経済産業大臣が認可する際には、原子力の平和利用やプルトニウムの需給バランス確保の観点から、原子力委員会の意見を聴くものとし、その意見を十分に斟酌して認可の適否を判断するものとすること。
- 5月11日
- 再処理等拠出金法成立、(18日公布)
- 10月3日
- 再処理等拠出金法に基づき再処理機構設立
- 12月14日
- 原子力規制委員会、第49回臨時会議(pdf)で平和利用について日本原燃に尋ねる
*議事録関連部分抜粋 - 2017年4月19日
- 原子力委、平和利用に関する行政組織は同委と回答(pdf)
*4月11日付の規制委からの質問に答えて - 7月20日
- 原子力委「原子力利用に関する基本的考え方」決定 (翌日閣議決定)
*削減の必要性についての国際的関心のため、現在、唯一の現実的な手段である軽水炉でのMOX利用での対応が求められ、日本の方針を「適切に説明」することが重要と。 - 10月3日
- 原子力委「日本のプルトニウム利用について【解説】」(pdf)
について議論・決定*六ヶ所再処理工場操業開始までに電気事業者が、「最新の実績を踏まえた新たなプルトニウム利用計画を公表し、国(原子力委員会)がその妥当性を確認……以上のことから……長期的に、日本のプルトニウム保有量の削減という目標が達成されるであろうと認識している」
阿部委員長代理「ここは非常に重要な文章で、原子力委員会としては減っていくと、こういう認識であると、こういうことですね。川渕さん、この長期的にって、どのぐらいの期間を考えられておられるんですか?」
川渕英雄企画官「えーっと、まあ非常に難しいところでありますけれども(笑い)、あの、えー、まあ、あの、そこまではまだ検討はしていないということ。」
- 2018年1月16日
- 原子力委、2003年の「わが国のプルトニウム利用の基本的考え方」の改訂作業をすると決定
岡委員長発言国際原子力機関の保障措置を初め核不拡散の優等生であるというようなところ。それから、最近、商業用のプルトニウムについて再処理機構というのができまして、経産省はその計画を認可するということで、国も民間の再処理事業の計画を見ることができるようになったというようなところが重要なメッセージかと…今後の在り方についてということで、平成15年のときのは、そのときとしてはよかった、適切だったのだろうと思いますが、利用目的のないという言い方は少し曖昧であるというところもあって、もう少しアップデートしていくことは日本として必要ではないかということで、その検討をする必要があるのではないかというふうに思います。
出典:議事録(pdf)
資料:日本のプルトニウム利用の現状と課題 2018年1月16日(pdf) 原子力委員会
日本のプルトニウムはこれら[再処理工場及びMOX燃料加工工場]の稼働当初は多少の増減はあるが、「長期的には、日本のプルトニウム保有量を削減するという目標を達成する」ことが必要。
- 4月3日
- 原子力委、「プルトニウム利用の考え方について」に関する議論
議事録(pdf)資源エネルギー庁:…既に実施中期計画は策定をしておりますけれども、六ケ所の再処理工場、MOX加工工場がまだ竣工まで時間があるということで、具体的な再処理量ですとかMOXの加工量というのは現在の実施中期計画にはまだ書かれておりませんけれども、将来的にそうした定量的な内容も盛り込んだ計画にするということです。
いずれにしましても、将来的にはそうした定量的な計画を策定し、それを原子力委員会の意見を斟酌した上で経済産業大臣が認可をする、こうしたスキームを通じて利用目的のないプルトニウムを持たない、こういう原則がしっかりと堅持をされるようにしていくということでございます。
配布資料:
- 1-1.研究開発用プルトニウムの利用に関する考え方について 平成30年4月3日(pdf) 文部科学省
- 1-2.我が国におけるプルトニウム管理・利用について 平成30年4月3日(pdf) 資源エネルギー庁
- 7月3日
- エネルギー基本計画(pdf)閣議決定
平和的利用を大前提に、核不拡散へ貢献し、国際的な理解を得ながら取組を着実に進めるため、利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を引き続き堅持し、プルトニウム保有量の削減に取り組む。これを実効性あるものとするため、プルトニウムの回収と利用のバランスを十分に考慮しつつ、プルサーマルの一層の推進や、2016年に新たに導入した再処理等拠出金法の枠組みに基づく国の関与等によりプルトニウムの適切な管理と利用を行う。
- 7月31日
- 原子力委、我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方(pdf)決定
*結論は「我が国は、上記の考え方に基づき、プルトニウム保有量を減少させる。プルトニウム保有量は、以下の措置の実現に基づき、現在の水準を超えることはない」というもの。
2018年1月16日の会議で岡委員長は、「利用目的のないという言い方は少し曖昧であるというところもあって、もう少しアップデートしていくことは日本として必要」と述べていたが、同じ表現が以下のように踏襲されている。
我が国の原子力利用は、原子力基本法にのっとり、「利用目的のないプルトニウムは持たない」という原則を堅持し、厳に平和の目的に限り行われてきた。...
*「利用目的を記載した利用計画」というのは、2003年8月決定の「考え方」にある「プルトニウム利用計画の公表」にある内容と変わりがない。
加えて、透明性を高める観点から、今後、電気事業者及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)は、プルトニウムの所有者、所有量及び利用目的を記載した利用計画を改めて策定した上で、毎年度公表していくこととする。
参考
関連記事
日経産業新聞
- プルトニウム管理、所管はどこ(サイクル政策の蹉跌2) 第1部 日米原子力協定 2019年3月19日
核情報
- 余剰プルトニウムを持たない国際公約とは? 2005.12.12~
- 「余剰プルトニウムを持たない」方針は、1997年に突然でてきたのか。
- 見えない新原子力委員会の役割 2015. 1.30
- 再処理永久化法10月1日施行の計画──資料整理 2016. 5.27
- 原子力委員会の滑稽な論議──プルトニウム利用について 2017.11.27
- なおざりなプルトニウム管理 再処理委託先の英国で核兵器約3000発分が「放置」 2018. 5.25
- 六ヶ所・再処理・高速炉関連記事類
六ヶ所再処理工場ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵容量:60トン(プルトニウムだけだと30トン)
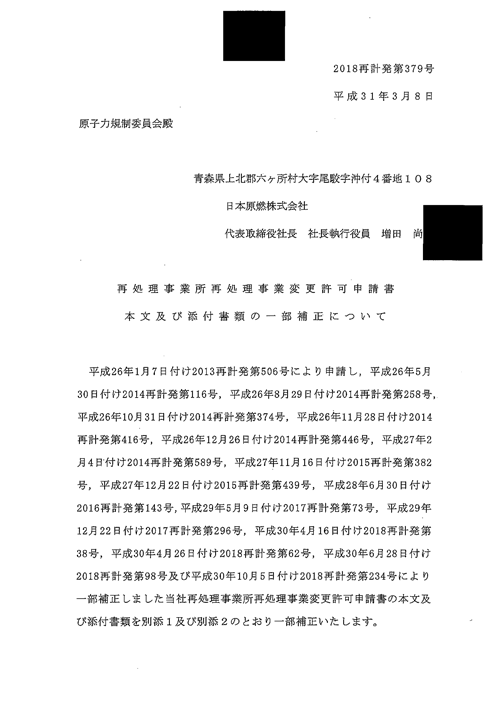
- 日本原燃の六ヶ所再処理施設に関する事業変更許可申請の一部補正文書(2019年3月8日)の再処理事業変更許可申請書の一部補正(本文(1))(pdf) 208-209ページ
(2) 主要な設備及び機器の種類…
(ii)ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
混合酸化物貯蔵容器 1式(MOX燃料加工施設と供用)
材料 ステンレス鋼
容量 粉末缶3缶/貯蔵容器
(粉末缶容量は約12㎏・((U:Pu))
貯蔵ホール
構成 ホール 1,680本
(混合酸化物貯蔵容器1本/ホール)・・・
(3)貯蔵する製品の種類及びその種類ごとの最大貯蔵能力…
(i)貯蔵する製品の種類…
(b)ウラン・プルトニウムの混合物(ウラン・プルトニウム混合酸化物)
貯蔵施設
(ii) 最大貯蔵能力…
(b) ウランとプルトニウムの混合物(ウランとプルトニウムの重量混合比は1対1)
60t・(U+Pu)
六ヶ所MOX燃料製造工場貯蔵容量:プルトニウム最大約36トン?
- 日本原燃(株)からMOX燃料加工施設に関する事業変更許可に係る申請の一部補正を受理(平成31年03月08日原子力規制委員会)の加工事業変更許可申請書一部補正(4)(pdf) 333-337ページより記載情報からプルトニウム貯蔵容量(tPu)をまとめると:
貯蔵容器一時時保管庫 1.2t・HM 富化度上限60% = 0.72tPu
粉末調整第一室 0.3t・HM 富化度上限60% = 0.18tPu
粉末一時保管室 6.1t・HM 富化度上限60%(ただし1.46tPuを上限) = 1.46tPu
ペレット一時保管室 1.7t・HM 富化度上限18% = 0.3tPu
ペレット・スクラップ貯蔵室 スクラップ 10t・HM 富化度上限18%(ただし1.62tPuを上限) = 1.62tPu
ペレット・スクラップ貯蔵室 ペレット 6.3t・HM 富化度上限18% = 1.13tPu
燃料棒貯蔵室 60t・HM 富化度上限18%(ただし4.66tPuを上限) = 4.66tPu
燃料集合体貯蔵室 170t・HM 富化度上限18%(ただし14.66tPuを上限) = 14.66tPu
輸送容器保管室 65t・HM 富化度上限18% = 11.7tPu
*合計すると最大 36.43t?以上整理は原子力資料情報室
六ヶ所再処理工場における年間プルトニウム分離量
経済協力開発機構/原子力機関(OECD-NEA)のデータ:年間800トン処理なら約8トン
- Plutonium Fuel - an assesement - Nuclear Energy Agency (pdf)
表9 PWRウラン燃料 1トンの燃料の同位体組成 (41ページ)PWR URANIUN FUEL
ISOTOPIC BALANCE FOR ONE TONNE OF FUEL(as weight per tonne in [kg] and as percentage [%] of total U for uranium and
of total Pu + Am for plutonium and for americium)
* Pu total + Am.ISOTOPE:
UNIT:FUEL SPEC
U-235 U-236 U-238 U-tot Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242 Am-241 Pu-tot* Pu/Pu + U** kg % kg % kg % kg kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg % 3.25% U-235+
33000MWd/t++32.5 3.25 0.0 0.0 967.5 96.75 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.84 0.92 3.91 0.41 943.72 98.67 956.47 0.12 1.26 5.4 56.62 2.21 23.18 1.32 13.86 0.45 4.73 0.03 0.35 9.54 0.99 3.70% U-235+
43000MWd/t++37.0 3.70 0.0 0.0 963.0 96.3 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.8 4.81 0.51 932.5 98.69 944.91 0.21 1.97 5.72 52.55 2.62 24.09 1.6 14.73 0.68 6.22 0.05 0.44 10.89 1.14 4.40% U-235+
53000MWd/t++44.0 4.4 0.0 0.0 956 95.6 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.68 0.82 5.94 0.64 919.83 98.54 933.44 0.33 2.74 6.07 50.37 2.91 24.15 1.83 15.16 0.85 7.06 0.06 0.51 12.05 1.27
** Pu total + Am/Pu total + Am + U total
+ Before irradiation.
++ After irradiation.上の表は、加圧水型原子炉で使用した燃料を炉から取り出した時点での同位体組成を燃焼度(燃やしたレベル)別に示したもの。右から2番目のPu-tot*は、プルトニウムのすべての同位体の合計とアメリシウム(プルトニウム241の崩壊で生じる)を合わせたものを示すと注にある(* Pu total + Am)。例えば燃焼度43000MWd/tの場合、全プルトニウム量は、10.89kg-0.05kg=10.84㎏。半減期14.4年のプルトニウム241(1.6㎏)は、14.4年経つと0.8㎏となっている。つまり、10.84kg-0.8kg=10.4kgが1トンの使用済み燃料に含まれている。
このような計算から、燃焼度33000MWd/t、43000MWd/t、53000MWd/tの1トンの使用済み燃料が、炉から取り出して15年後に含んでいるプルトニウムの量は、それぞれ、約9、10、11㎏となり、800トンを処理すると、それぞれ、約7、8、9トンが分離されることになる。
日本原燃 1996年4月再処理事業所再処理事業変更許可申請書
では年間8トン(2ページ目の表「予定生産量」)
*ウラン・プルトニウム混合酸化物(ウランとプルトニウムの重量混合比は1対1)製品の製造を2002年に始め、製造量が2007年に年間16トン(金属ウラン及び金属プルトニウムの合計重量換算)に達することを示している。プルトニウムの量は8トン。(同申請書(pdf)は原子力資料情報室提供。)
- 日本原燃2014年再処理事業所再処理事業変更許可申請書(pdf)(98/215)及び
- 2019年3月8日提出の再処理事業変更許可申請一部補正
添付資料2(pdf)(13/61)では、年間7トン(混合酸化物製品14トン)
予定再処理量・生産量
上記「添付資料2」より作成
年度 種類
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 再処理量
(t・Upr)BWR使用済
ウラン燃料48 192 288 640 800 800 800 800 800 800 800 PWR使用済
ウラン燃料32 128 192 生産量 ウラン酸化物
(t・U)73 293 439 586 732 732 732 732 732 732 732 Pu混合酸化物
(t・(U+Pu))1 6 9 11 14 14 14 14 14 14 14 *<再処理工場>操業開始年度の再処理量80トン 原燃、計画提出 河北新報(2019年2月1日)によると、日本原燃が想定している2021年度下期の操業というのは、2022年1月―3月の稼働で80トンの使用済み燃料を再処理するというもの。上の表は、2025年度にフル操業を達成して800トンを処理し、7トンのプルトニウムを取り出す計画であることを示している。
日本原燃の想定する再処理までの冷却期間 15年以上
- 原子力規制委員会第238回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合(2018年7月6日)へ提出の「六ヶ所再処理施設における新規制基準への適合性について」(pdf)(36ページ)
…せん断処理するまでの冷却期間を15年以上とする。
旧申請書等における再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能力の記載事項のうち、冷却期間については、再処理施設にを受け入れるまでの冷却期間を1年以上、せん断処理するまでの冷却期間を4年以上であった。*上記のOECD-NEAのデータにある燃焼度33000MWd/tレベルの使用済み燃料をプルトニウム241の半減期に相当する期間以上冷却してからの再処理との想定で、分離量が低めとなっていると見られる。
2016年12月14日原子力規制委員会第49回臨時会議・議事録(pdf) 関連部分抜粋(19-23ページ)
○田中知委員
今、再処理施設の新規制基準適合性の審査を行っているところでございますが、確認が終了して施設が稼働することとなった場合には、分離プルトニウムの在庫が蓄積していくことになるのではと考えています。これに関連して、平和利用に関連しての基礎的な知識として理解したいといいましょうか、それで質問したいところでございます。我が国は利用目的のないプルトニウムを保有しないという原則といいましょうか、そういう政策をとっていることは承知しているわけですけれども、再処理の事業者として、自らが分離するプルトニウムが平和利用目的のないプルトニウムかどうかを今後どう判断していくのかについて、もし考えるところがあれば、教えていただきたいと思います。もちろん、これは政策的なことですから、政府のどこかが判断することになるかもしれませんし、その中で明確な判断基準を定めていくかわからないのですけれども、その辺の状況について、日本原燃として、当事者としてどういう認識を持っているのか、教えていただければと思います。
○工藤日本原燃株式会社代表取締役社長
御質問の趣旨は、今後稼働していけばプルトニウムが出てくると。利用目的のないプルトニウムを持たないということとの関係で、消費が進まなければちょっとあれだなという、その辺の流れ、今の状況についてどう思うかという御質問でございますか。
○田中知委員
その辺について、日本原燃として、将来どういう判断というか、判断の基準というか、何かを考えようとしているのか、あるいは日本原燃だけでは考えられないのか、その辺の認識を教えていただきたいのです。
○工藤日本原燃株式会社代表取締役社長
政策的に利用目的のないプルトニウムを持たないというのは大原則、大前提でございます。これはグローバルな意味でもまさにそうだという認識はしっかり持っています。私どもが確立を目指しております、いわゆる軽水炉サイクルというものにつきましては、MOX(混合酸化物)燃料工場でMOX燃料にしていくと。それは、軽水炉のプルサーマルでしっかり消費していくと、こういう状況でございまして、私が申すまでもございませんけれども、原子力発電所の再稼働がこういう状況でございますので、かつて予定していた状況に対して、非常に厳しくなっているということはございます。ただ、平和利用目的のないプルトニウムを持たないのだという原則を踏まえれば、電力各社が一丸となって、しっかりプルサーマルを進めていくということが極めて重要であると私は思っております。
○田中知委員
プルサーマルを進めていくということはわかるのですけれども、具体的に、再処理から出てくる分離プルトニウムの量等について、日本原燃として何がしかの判断基準を持たないといけないと考えるのか、どうなのか、その辺についてなのですが。
○工藤日本原燃株式会社代表取締役社長
御趣旨が、ごめんなさい。
○田中委員長
日本原燃だけで判断できなくて、懸念はされているだろうと思うのですね。そのあたりも含めて、正直なところを、言える範囲で結構ですので。多分、田中知委員はそのことを言っているのだと思います。プルトニウムリサイクルというのは一つの国策ですから、多分、日本原燃だけで言えることではないと思います。
○工藤日本原燃株式会社代表取締役社長
懸念という意味では、先ほどの繰り返しになりますけれども、しっかり消費されていかなくてはいけない。私どもで、プルトニウムの生産の工程がございますから、利用目的のないものを持っているということではなくて、ある程度の在庫を持つというのは、当然許容されてしかるべきだとは思っていますが、真の消費というのが、これは是非、済みません、先ほどと同じことになりますけれども、電力会社の方でプルサーマルをしっかり進めていただくことに強い期待をしているということに尽きるわけです。
○村上日本原燃株式会社副社長執行役員
すみません、ちょっとよろしいですか。再処理事業部長で、使用計画とか、その大もとを検討している立場から申し上げますと、基本的には、使用済燃料の受け入れとか、あとは処理量、それは電力とのニーズで調整してやると。基本的には、電気事業連合会が前に原子力委員会の場で公表していますように、再処理が稼働するまでにはプルサーマル利用の計画を明らかにするということで、そういったことを前提に今後調整していくことになると思います。
以上です。
○更田委員長代理
ちょっと別の聞き方をします。同じ質問なのですが。要するに、どういう状態のプルトニウムがどれだけたまると過剰ということになるのかと。それは自社で判断をされるのか、あるいはどこかの判断を仰ぐことになるのか。例えば、その状態にもよって、プルトニウム溶液なのか、酸化粉末にする、あるいはMOX燃料になってしまえば核拡散抵抗性はかなり上がるだろうとは思われますけれども、生産と消費のバランスがあって一定の在庫を持たざるを得ないというのはもちろん当然のことだと思うのですが、では、在庫が膨れ上がってしまっていいかというと、そういうものではない。やはり消費される以上のプルトニウムは生産しないという観点からすれば、過剰にならないという判断をする必要があると思うのです。それはどうされるのでしょう。
○村上日本原燃株式会社副社長執行役員
よろしいですか。村上ですけれども、その一つの目安として、安全審査のときも議論があって、MOX工場の在庫としてはどのぐらいが適切かという議論がありまして、今、在庫としては60トンHMですか、そこを基準として、再処理のトラブルがあった場合、MOX工場のトラブルがあった場合とか、その流用を考えて、そこの必要量を適正だと議論されて判断しております。
○更田委員長代理
60トンHMというのは、どういう状態でですか。硝酸液ですか。
○村上日本原燃株式会社副社長執行役員
いえ、金属酸化物として、粉末です。
○更田委員長代理
粉末でですか。
○田中知委員
その辺のところは、いろいろなプロセスをやっていくときには必要だという観点だと思うのですが、利用目的のないプルトニウムを保有しないという、大きな政策的なことからいったときに、どのぐらいの量ならば、いわゆる平和利用目的のないプルトニウムを持っていないという政策とうまくマッチするのかというのは、もしかしたら日本原燃だけでは決められない話かもわからないのだけれども、その辺について、日本原燃だけで決められないことと理解してよろしいのでしょうか。やはり国全体の話でもありますから。
○工藤日本原燃株式会社代表取締役社長
すみません、先ほどは失礼いたしました。御質問の趣旨はよくわかりました。それは私どもだけではなくて、国際の話につながるわけでございますから、御当局というのは、どこが御当局になりますかね。
○村上日本原燃株式会社副社長執行役員
使用済燃料再処理機構が絡んで、そこから委託を受けるという形式がありますので。ただ、大もとのプルサーマルやプラントは各電力会社ですので、全体を取りまとめるのは電気事業連合会ということになりますけれども、そこと調整が現時点では必要になってくると。
○工藤日本原燃株式会社代表取締役社長
だから、重なりますけれども、私どもだけでこうだという判断はなかなか難しいかなと思います。
○田中委員長
私どもの立場から、先ほどから田中知委員が繰り返しているように、利用目的のないプルトニウムを持つというのは、核セキュリティを担当している部門としては非常に好ましくないということがあります。ですから、いずれ遠くない時期に再処理工場が稼働したときに、相当量のプルトニウムが生産されると。プルトニウムの性質上、処理したら早く使う方がいいわけで、その辺の道筋がきちっとできないときに、どうするのだろうかと、かなり難しい状況なのですね。社長が電気事業者が努力して早く再稼働をと言っても、これは新規制基準にきちっと適合していただかなければいけないわけで、そういうことから言うと、そうすいすいといくような話ではないので、そこのあたりをどうするのかなと。どこが一体それを決めるのか。先ほど副社長は、電気事業連合会と、あるいは再処理機構とという話ですけれども、そこだけに閉じていて物事が解決するのだろうかという気がするので、私どもとしても、この問題は別の点でしかるべく、どこかに問い合わせないと、どこかの時点でそういう議論をさせていただかなければいけないのではないかという気がするのですね、許可を出すときに。ですから、その辺も含んでおいていただければと思います。
○更田委員長代理
委員長のおっしゃったことをより具体的にですけれども、安全とセキュリティ等々に関して審査を行って、許可を判断するときには、経済産業大臣と原子力委員会に諮問をして、それぞれの目的、それぞれの責任感における判断を受けた上で許可ということになるわけです。原子力委員会は平和利用目的の事業であるという観点から判断をされるのだろうと思いますが、そのときに、何らの判断材料を持たずに、例えば、これは日本原燃がやる事業であるからといった理由で平和利用目的だという判断はなかなか下しづらいところがあるだろうと思います。そこが、先ほど副社長がおっしゃった、粉末で60トンHMまでを上限とするとか、そういった具体的なもの、もちろん生産側としては、在庫量は事業の裕度を増すものであるから、これ以上小さいとなかなかというところはあるでしょうけれども、一方、認める側は認める側で、ここまでであればという範囲があると思う。これについては、私たちは今、安全に関して、田中知委員のもとで審査が行われてはいるけれども、その許可ないし不許可の判断をするまでには、状況を整備される一環として、まず、日本原燃としてどう考えておられるかを伺うのも重要であるだろうけれども、平和利用目的という判断をするときに、なかなか判断材料といいますか、レベルが整っていない状況なのではないかという懸念を持っています。ですから、これについての議論は私たちの方としても、これは原子力規制委員会だけではなくて、今、申し上げた経済産業大臣、原子力委員会ですか、どこがどう判断のための環境をつくっていくかということは重要であると思っていますし、また事業者として日本原燃もその問題意識を持っていただきたいと思います。
○工藤日本原燃株式会社代表取締役社長
おっしゃっている御趣旨はよくわかります。例えば、原子力委員会等々でどのような御判断がされているかというのは、今、詳細な状況を承知していませんので、今の御指摘につきましては、早速、どうなっているか、勉強なり、私どもとして何ができるのかということを考えてみたいと思います。今日の段階では、そういう御趣旨のお話を承るということにとどめさせていただきます。
○田中委員長
この問題はなかなか根っこが深い問題ですから、今日、明日にいい答えが出るという話ではないと思いますので、頭の隅に置いていただくと。私どもも別の観点から、そういう関心を持ちながら規制をさせていただくということで、今日はこれぐらいにしておきたいと思うのですけれども、よろしいですか。